はじめに
「もし自分や家族に万が一のことがあったら、生活はどうなるのだろう…」
そんな不安を感じたときに支えとなるのが遺族年金です。
ただし遺族年金は「誰が受け取れるのか」「いくらもらえるのか」「いつまで支給されるのか」が複雑で、年収や子どもの有無、配偶者の年齢などによって金額が大きく変わります。さらに、2025年の制度改正で中高齢寡婦加算が段階的に廃止されるなど、将来の設計にも影響を及ぼすポイントが出てきています。
この記事では、遺族年金の仕組みと金額シミュレーション、年齢や家族構成による違い、そして改正後に注意すべき点をわかりやすく解説します。読んだあとには「自分の場合はどうなるのか」がイメージでき、将来の備えについて考える第一歩となるはずです。
1. 遺族年金の基礎知識
 相談者さま
相談者さま「遺族年金って一体どんな制度なんですか? 正直、仕組みがよくわからなくて…」



「簡単に言うと『家族が亡くなったときに遺族を支える年金』です。国民年金と厚生年金の“二階建て”で構成されているんですよ。」
遺族年金は、日本の公的年金制度の中で、家族を失った遺族の生活を支える大切な仕組みです。
基本的には「二階建て構造」になっていて、次の2種類に分けられます。
- 遺族基礎年金(1階部分)
国民年金に相当する部分で、子どものいる配偶者、または子ども自身に支給される定額の年金です。
ポイントは「子どもの有無」が受給の大前提になっていることです。 - 遺族厚生年金(2階部分)
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給されるもので、遺族基礎年金に上乗せされます。金額は亡くなった方の平均年収(標準報酬)や加入期間によって変動します。
つまり、遺族年金の金額や受給資格は、「加入していた年金の種類」+「遺族の家族構成」によって決まります。
2. 遺族基礎年金:受給できる人と条件



「夫が亡くなったら、必ず遺族基礎年金がもらえるんですよね?」



「実はそうではないんです。遺族基礎年金は“子どものいる配偶者”か“子ども本人”に限られていて、子どもがいない配偶者には支給されません。」
遺族基礎年金は、国民年金にあたる1階部分の制度で、死亡した方が一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
受給できる人
- 子どものある配偶者
- 子ども(18歳到達年度の末日まで、または障害等級1級・2級なら20歳未満)
👉 子どもがいない配偶者は、対象外となる点が大きな特徴です。
子どもの加算
- 第1・第2子 … 各23万9,300円
- 第3子以降 … 各7万9,800円
支給が終わるタイミング
子どもが18歳に達する年度末を迎えると、配偶者も含めて遺族基礎年金の受給資格が消滅します。
3. 遺族厚生年金:報酬比例で決まる金額



「遺族厚生年金って、どれくらいもらえるんでしょうか?」



「金額は、亡くなった方の“平均年収”と“加入期間”に比例します。つまり収入が高いほど受給額も大きくなる仕組みなんです。」
計算の基本
- 老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4 が基本額
- 「平均標準報酬額(生涯の平均年収に近い指標)」をもとに計算
- 加入期間が25年に満たない場合でも「300月(25年)」とみなして計算
平均年収別のシミュレーション(加入40年想定)
- 年収400万円 → 約84.6万円/年
- 年収600万円 → 約126.9万円/年
- 年収800万円 → 約169.2万円/年
4. 妻の年齢による違い



「妻の年齢で、もらえる遺族年金って変わるんですか?」



「はい。40歳や65歳といった節目で受け取れる内容が大きく変わります。特に40歳未満だと“支援の谷間”が生まれるケースもあるんです。」
40歳未満の妻
- 子あり → 子が18歳まで受給可能
- 子なし → 遺族厚生年金のみ(中高齢寡婦加算なし)
40歳以上65歳未満の妻
- 子あり → 子が18歳到達後、中高齢寡婦加算(約62万円)がスタート
- 子なし → 夫の死亡時から中高齢寡婦加算を受給
👉 ただし、この加算は2025年以降、段階的に廃止予定
65歳以上の妻
- 自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給開始
- 遺族厚生年金は「自身の厚生年金との差額」が支給される(併給調整ルール)
5. 2025年改正のポイント



「ニュースで“中高齢寡婦加算がなくなる”って聞いたんですが、本当ですか?」



「はい、2025年の改正で段階的に廃止されます。40歳から65歳までの生活を支える大事な制度でしたが、今後の世代には適用されなくなるんです。」
- 中高齢寡婦加算の段階的廃止が決定
- 年間約62万円相当の支援が失われる
- 公的年金だけに頼れないため、民間保険や貯蓄での備えがより重要に
6. 自営業者の遺族年金と代替制度



「夫が自営業で国民年金だけなんですが、その場合でも遺族年金はもらえるんでしょうか?」



「はい、条件を満たせば遺族基礎年金は受け取れます。ただし厚生年金に加入していなかった場合、“遺族厚生年金”は支給されません。その代わり、寡婦年金や死亡一時金といった制度があります。」
自営業者の遺族給付
- 遺族厚生年金はなし
- 寡婦年金(夫が10年以上納付していた場合、妻が60〜65歳で受給)
- 死亡一時金(保険料3年以上納付で一度きりの支給)
👉 厚生年金の上乗せがないため、公的年金だけでは生活保障が不足しがち
7. まとめ



「結局、遺族年金ってどんな人がどれくらいもらえるのか、押さえておくべきポイントは何ですか?」



「大事なのは“3つの要素”です。①亡くなった方の年収、②子どもの有無と年齢、③妻の年齢。この3つで金額も受給期間も大きく変わります。」
押さえるべきポイント
- 亡くなった方の年収(報酬)
- 子どもの有無と年齢
- 妻の年齢(40歳・65歳)
今後の注意点
- 2025年以降、中高齢寡婦加算が廃止
- 自営業世帯は保障がさらに弱い
- 公的年金だけに頼るのはリスク
👉遺族年金を理解することは、もしもの時に家計を守る大切な準備です。
ご不安があれば、のどかFP事務所までお気軽にご相談ください。
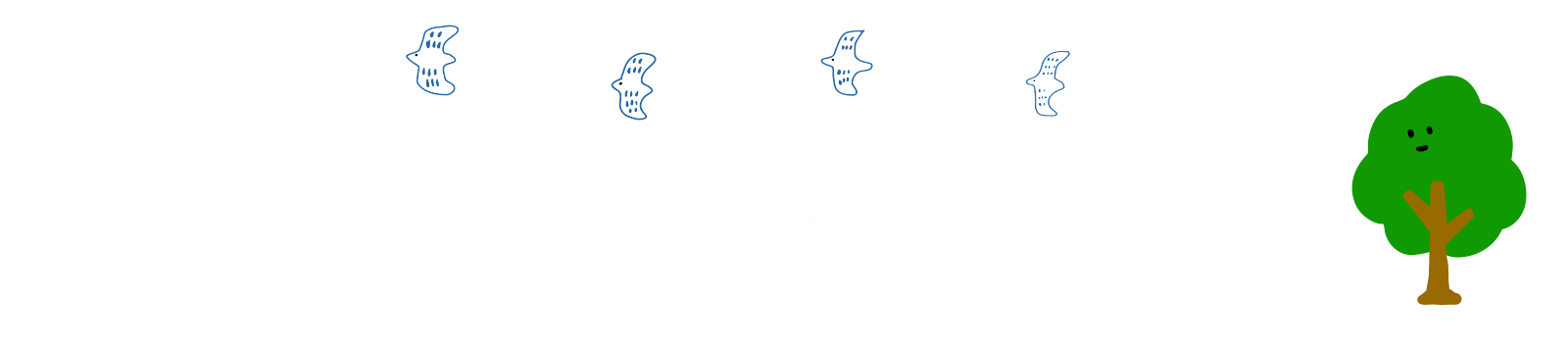

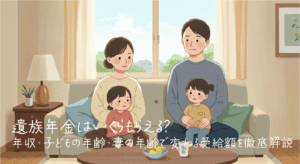
コメント