はじめに
 相談者さま
相談者さま「保険って、やっぱりいろいろ入っておいた方が安心ですよね?」



「そう思われる方は多いですが、実は日本の公的保障はとても手厚いんです。まずはそれを知った上で、足りない部分だけを民間保険で補うのが賢い選び方なんですよ」
保険に入りすぎて家計を圧迫している人は少なくありません。今回は、公的保障と民間保険の役割を整理しながら、FPの視点で「無駄のない保険の見直し方」を一緒に考えてみましょう。
第1章:保険選びの大前提



「でも保険って、“万が一のため”にとりあえず入っておくものじゃないんですか?」



「本来は“めったに起きないけど、起きたらお金が大きくかかるリスク”に備えるためのもの”なんです。たとえば、子どもが独立して資産も十分にあるのに高額な終身保険を続けている方もいますが、それは“安心料”を払いすぎている状態かもしれません」
不安な気持ちだけで保険を決めると、気づかないうちに大切なお金が保険料に流れていきます。まずは「どんなリスクに、どれくらい備える必要があるか」を整理することが大切です。
第2章:公的保障を正しく知る
民間の保険を検討する前に大事になることが、公的な保障、いわゆる社会保障の制度についてよく理解をし、活用することが大事になります。
医療費リスク:高額療養費制度



「もし入院したら、何百万円も請求されるんじゃないかと不安です…」



「実は、日本には“高額療養費制度”があって、1か月の自己負担額には上限があるんです。例えば年収370〜770万円の方なら月44,400円まで。住民税非課税世帯なら月24,600円です」
つまり、何百万も払わされるわけではありません。数万円程度なら、貯蓄でまかなえるご家庭も多いですよね。
死亡リスク:遺族年金



「もし私に何かあったら、家族の生活費が心配です…」



「遺族年金があるので、ある程度は国が支えてくれます。例えば標準報酬月額30万円だと、遺族厚生年金だけで年間約37万円。これに遺族基礎年金が加わります」
つまり「生活費のすべて」を保険で準備する必要はなく、「足りない分だけ」を定期保険でカバーすれば十分なんです。
所得喪失リスク:障害年金



「病気や事故で働けなくなったらどうしようって不安です…」



「その場合は障害年金が支給されます。2級で年額約83万円、1級だと104万円ほどに加えて子の加算もあります」
だから民間の就労不能保険に入るなら、障害年金との差額や支給までのタイムラグを補う形で加入するのが合理的なんです。
第3章:民間保険が本当に必要な場面



「じゃあ、民間の保険っていらないんですか?」



「いえ、必要な場面もあります。ただし“公的保障でカバーできない部分だけ”を補えばOKです。」
- 子育て中は大きな死亡保障が必要 → 掛け捨ての定期保険で対応
- 自転車事故や日常の賠償リスク → 個人賠償責任保険で備える
民間保険は「ピンポイントで不足分を埋めるもの」と考えた方が効率的です。
第4章:貯蓄と運用は別で考えよう



「学資保険や終身保険で積み立てもしてるんですが、それで安心ですよね?」



「実は保険で貯めるのは効率があまり良くないんです。保険料が高かったり、途中で解約すると元本割れすることも多いです。」
その代わりに、資産形成はNISAやiDeCoを活用するのがオススメです。
- iDeCo:掛金が全額所得控除、運用益非課税、老後資金づくりに強力
- 新NISA:運用益非課税で、必要なときに引き出せる柔軟さ
保険は“保障”、資産形成は“NISAやiDeCo”。この分け方が無駄のない方法です。
第5章:ライフステージごとに見直す



「一度入ったら、ずっと続けておけば安心じゃないんですか?」



「いえ、保険はライフステージごとに必要な保障が変わります。だから見直しが欠かせないんです。」
- 子育て期:定期保険で大きな死亡保障を確保
- 子ども独立後:保障を減らし、余ったお金は資産形成へ
- 退職後:医療や介護は公的制度+貯蓄で対応
加入したまま放置すると、必要ない保険料を払い続けることになりがちです。
まとめ



「なるほど…今まで“安心のために”と入ってきましたが、見直す必要がありそうですね。」



「そうですね。大事なのは次のステップです。」
- リスクを整理する(死亡・医療・所得喪失・賠償)
- 公的保障を確認する
- 足りない部分を計算する
- 定期保険など掛け捨てでカバーする
- 資産形成はNISA・iDeCoで
保険は「安心料」ではなく「家計を効率よく守るツール」。
公的保障を土台に、不足分だけを民間保険で補う。そのバランスを意識すれば、無理なく家計を守りながら、将来の安心も確保できます。
「保険って複雑で、自分にとって何が必要なのか分かりにくいですよね。私たちFP事務所では、公的保障と家計状況を踏まえて“本当に必要な保障”を一緒に整理します。無駄な保険料を減らしながら、将来の安心も守りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。」
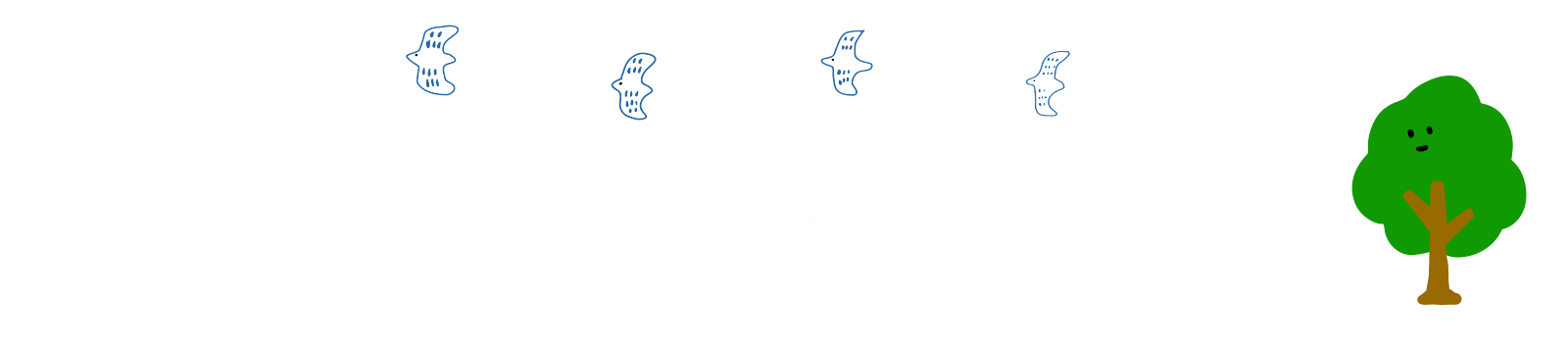


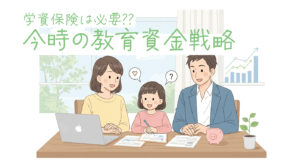
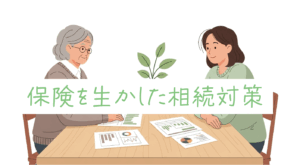
コメント